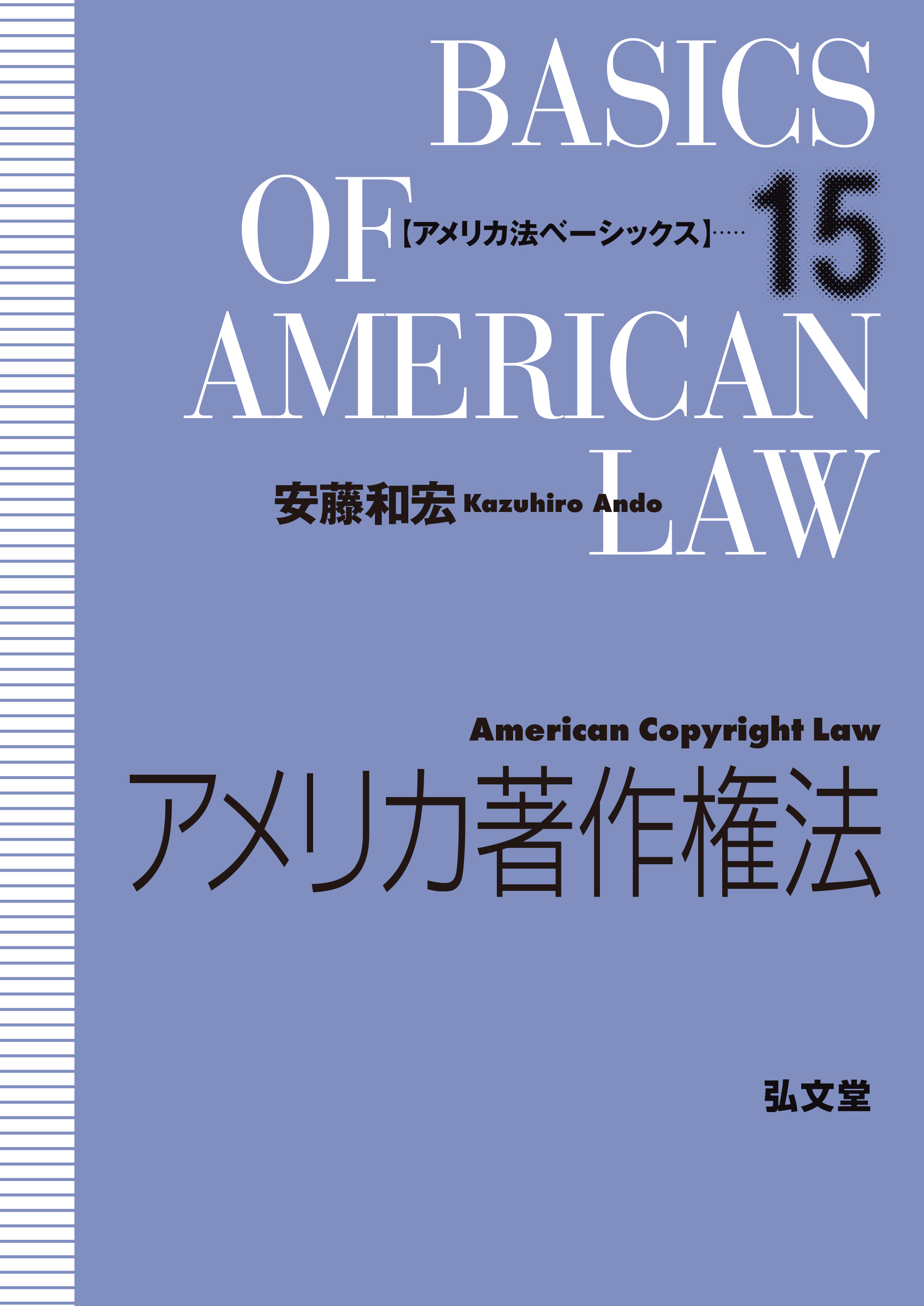アメリカ著作権法
Author: セプティマ・レイ
■著者:安藤和宏
■仕様:A5上製・408ページ
■価格:4,100円(+税)
■発売日:2025.5.27
■ISBN-13:978-4-335-30388-3
世界一のエンタメ大国は、創作をどのように促進しているか
映画や音楽の分野において、世界最大の市場を誇るアメリカ。
同じエンターテインメント大国であっても、フェア・ユースや終了権、破壊防止権など、その制度設計や拠って立つ思想は、日本とは大きく異なります。
その特徴と魅力を、クリエイターを支える実務家としても百戦錬磨の著者が、手に取るように鮮やかな判例解説とともに描きます。
アメリカの著作権制度を深く理解するための、初めての概説書!
●目次
第1章 アメリカ著作権法への招待
Ⅰ アメリカの連邦裁判制度―著作権問題は連邦裁判所の管轄―
Ⅱ 著作権法の歴史的変遷―1790年法から1909年法、そして1976年法へ―
Ⅲ 著作権制度の意義―著作権の正当化根拠―
第2章 著作権の保護要件と登録制度
Ⅰ どのような創作物に著作権が付与されるのか―方式主義から無方式主義へ―
Ⅱ 形式的要件―表示制度と登録制度のメリットとは―
Ⅲ 著作権法の保護を受けない情報―知らないと必ず損する―
第3章 著作権の保護対象
Ⅰ 言語著作物―言語で表現する創作物―
Ⅱ 音楽著作物―音で表現する創作物―
Ⅲ 演劇著作物―ストーリーで表現する創作物―
Ⅳ 無言劇および舞踊の著作物―身体の動きで表現する創作物―
Ⅴ 絵画、グラフィックおよび彫刻の著作物―応用美術という永遠の難題―
Ⅵ 映画その他の視聴覚著作物―映像で表現する創作物―
Ⅶ 録音物―音声の保護―
Ⅷ 建築著作物―最後に仲間入りをした著作物―
Ⅸ 編集著作物―編集で表現する創作物―
Ⅹ 二次的著作物―親亀の背中に子亀を乗せて―
第4章 著作権の主体
Ⅰ AI生成物の著作者は誰か―創作的寄与というメルクマール―
Ⅱ 共同著作物―チームで作る著作物―
III 職務著作物―日々大量に作成されている著作物―
第5章 権利の移転と未知の利用方法
Ⅰ 権利移転と移転の優劣を決める登録制度―騙されないための必須知識―
Ⅱ 権利移転に係る契約の解釈方法―厳格解釈アプローチと合理的解釈アプローチ―
Ⅲ 未知の利用方法の契約解釈に関する裁判例―悩める裁判官たち―
Ⅳ 厳格解釈アプローチか合理的解釈アプローチか―単独利用型と素材利用型―
第6章 保護期間
Ⅰ 度重なる法改正で長期化する保護期間―登録日起算から発行時起算、そして死亡時起算へ―
Ⅱ なぜ1976 年法で死亡時起算主義を導入したのか―下院報告書の説明―
Ⅲ ミッキーマウスを延命させたソニー・ボノ法―ミッキーを救え!―
Ⅳ ソニー・ボノ法は違憲なのか―連邦最高裁の判断やいかに―
Ⅴ 「著作者の死亡時期がわからない……」―そんな貴兄のための推定制度―
第7章 終了権制度
Ⅰ 更新制度―最初の保護期間+更新期間―
Ⅱ 終了権制度―著作者に契約のチャンスは2度必要―
Ⅲ 終了権制度の新たな効用―作品の死蔵防止効果―
第8章 モラル・ライツ
Ⅰ 視覚芸術作品の保護制度―アメリカ独自の法制度―
Ⅱ VARAによる視覚芸術作品の保護―連邦法のモラル・ライツ―
III 名声が認められる著作物を巡る裁判例―芸術性の判断は難しい―
IV 破壊防止権制度の行方―破壊される芸術作品の運命やいかに―
第9章 排他的権利
Ⅰ 複製権―最も基本的な権利―
Ⅱ 翻案権―二次的著作物の作成に対する禁止権―
Ⅲ 頒布権―著作物の流通をコントロールする権利―
IV 公の実演権・展示権―著作物の無形的利用に対する禁止権―
V 録音物のデジタル音声送信権―ネットワーク時代の申し子―
第10章 フェア・ユース
Ⅰ フェア・ユースの歴史―起源は1841 年のFolsom v. Marsh―
Ⅱ フェア・ユースの4 つの要素―ファクター分析という判断手法―
Ⅲ フェア・ユースに関する主要な裁判例―重要裁判例が目白押し―
Ⅳ フェア・ユースを日本法に導入すべきか―議論は続くよ、どこまでも―
第11章 権利制限
Ⅰ 公の実演・展示に対する著作権の制限
Ⅱ 二次送信―アメリカ社会で大きな役割を果たすサービス―
Ⅲ 送信のための一時的固定に対する制限
Ⅳ 公共放送のための法定許諾制度
Ⅴ ジュークボックスによる実演
Ⅵ 音楽作品の録音に対する強制許諾制度
Ⅶ 録音物に対する著作権の制限
Ⅷ 絵画・グラフィック・彫刻の著作物に対する著作権の制限
Ⅸ 建築著作物に対する制限
Ⅹ 図書館や文書資料館による複製
Ⅺ コンピュータ・プログラムの複製・翻案
Ⅻ 障碍者のための複製・翻案
第12章 実演家の権利と保護
Ⅰ 契約法による保護―契約による正当な利益の確保―
Ⅱ 労働協約による保護―弱者の味方、労働組合―
Ⅲ 連邦著作権法による保護―職務著作物という名の難敵―
Ⅳ コモン・ロー上の著作権による保護―固定されていない著作物―
Ⅴ パブリシティ権による保護―有名人に与えられた強力な武器―
Ⅵ ランハム法による保護―不実表示からの保護―
Ⅶ 日本はアメリカ型の労働協約の確立・拡充を目指すべきか
第13章 侵害と救済
Ⅰ 著作権侵害を主張するための要件―勝訴するための条件とは―
Ⅱ 主要な裁判例―似てる・似てないは難しい―
Ⅲ 民事救済―権利者はどのような救済が受けられるか―
Ⅳ 刑事罰―拘禁刑と罰金―
第14章 間接侵害
Ⅰ 代位責任法理―いわゆる監督不行届責任―
Ⅱ 寄与侵害法理―侵害者を助けるとあなたも侵害者―
Ⅲ サイバースペースにおける間接侵害訴訟―P2Pサービスの登場―
第15章 DMCA
Ⅰ OSPに対する責任制限―OSP は法的に不安定な立場にいる―
Ⅱ 技術的手段の保護―DMCA は行きすぎた保護なのか―
Ⅲ 著作権管理情報の保護―その意義と禁止行為―
第16章 連邦法と州法の交錯
Ⅰ 連邦法と州法との関係―連邦法は州法に優越する―
Ⅱ 美術作品の著作者に付与される追及権とは―不遇な芸術家のための救済策―
Ⅲ カリフォルニア追及権法―全米で唯一の追及権法―
Ⅳ カリフォルニア追及権法と州際通商条項との関係―さらに試練は続く―
Ⅴ カリフォルニア追及権法の行方―生か・死か―